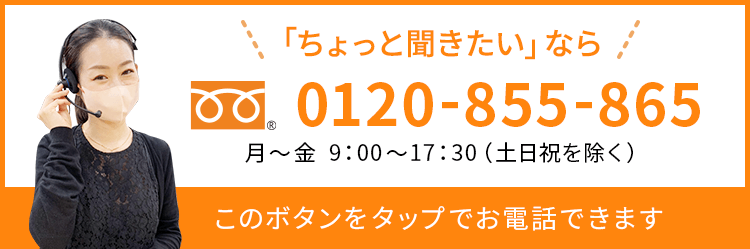建設業の請求書!清水や鹿島の現場もOK!効果的な作成方法

建設業の中小事業主が作成する請求書では、人工費や出来高払いなど、業界特有の言葉や請求方法が使われています。
請求書の様式も提出する会社ごとに異なりますよね。
わかりやすく正確な内容で請求書を作成することが信頼関係を保つために大切です。
この記事では中小事業主が確認すべき請求書の書き方や、また中小事業主が建設業許可を取るために請求書作成で注意すべき点について確認していきます。
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(特別労災)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1から、間違いありません。
1.建設業の請求書:請求書に必要な項目7個
建設業の中小事業主が工事を請け負う上では、工事代金の請求時期を契約書で取り決めておくのが一般的です。
その上で中小事業主が請求書を作成する際は、基本の7項目を明記しましょう。
①取引年月日
②請求書の宛先にあたる事業者の氏名または名称
③発行者の氏名または名称
④取引内容
⑤請求金額(税込み)
⑥振込先
⑦請求書番号
上記に加えて備考欄を設け、建設業の専門用語を説明したり、振込手数料負担について明記するとより丁寧でしょう。
2.建設業の請求書:建設業の請求書の特徴
請求書とは一般的に、顧客にサービスや商品を提供した後に、内訳や数量を明確にした上で代金を支払ってもらうために発行する書類です。
請求の内訳を書類として残すことで、サービス・商品の提供内容をチェックしたり、代金の未払いによるトラブルを防ぐことができます。
建設業の中小事業主の場合は工期の途中でも出来高払いの形で代金を請求する場合があるのが特徴です。
契約内容によっては、中小事業主が工事前の着手金を請求する場合もあります。
中間金の請求では工事の進捗状況を必ず確認するため、確認結果を工程に反映させて工事品質を向上させることができます。
工事関係者とコミュニケーションをとるチャンスも生まれるので、工事に関する思い違いも防止できます。
つまり、建設業の中小事業主が作成する請求書は単に代金を請求するだけでなく、工事状況のチェックツールとしての役割を持っているのです。
建設業の中小事業主が作成する請求書では、作業員1人あたりの1日分の人件費を「人工」という単位と表記する場面が多いです。
例えば、2日間で作業員5人が工事に携わった場合は「10人工」と表記します。
中小事業主が人工費を請求する場合も、一般的な請求書と同じように以下の内容を記載します。
・請求日
・請求内訳
・人工の数量
・単価
・消費税額
・税込請求額
請求内訳には、作業員の人数・稼働した日数と工事名を明記します。
人工費は外注費にあたるので消費税も一緒に請求します。
また、中小事業主が一般顧客へ請求書を発行する場合、専門用語をできるだけ使わないよう配慮すると工事内容を説明しようという気持ちが顧客に伝わり、信頼獲得につながるでしょう。
どうしても一般的な言葉への置き換えが難しい場合は、請求書の備考欄などで詳細を説明するようにしましょう。
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(特別労災)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1から、間違いありません。
3.建設業の請求書:大手ゼネコンも推奨する請求書の書き方
大手ゼネコンが推奨する請求書とは、どのようなものでしょうか。
大手ゼネコンのほとんどが、取引をスムーズにするため、中小事業主等の取引先向けに指定の請求書フォーマットを用意しています。
清水建設
https://procure.construction-ec.com/payment/jsp/owner/408142906891/paymentadvice/guest/st/faq/tejunsyo_seikyusyoshiki_torikime.pdf
鹿島建設
https://www.kajima-tatemono.com/dl/dl.html
大手ゼネコンの用意する請求書フォーマットでは、取極金額や契約明細などの「契約時の金額」と「請求額」を明記するようになっています。
前述したように、建設業では工事の完了前でも着手金や出来高払いの形で中間金を請求するのが主流です。
中小事業主のみなさんは工期途中で資金繰りに困らないよう、出来高検査を行う時期と基準を明確にした上で確実に代金を受け取れるよう準備しておきましょう。
追加工事や工事の不適合が発生した場合の対応方法についても取り決めておくようにします。
4.建設業の請求書:建設業許可を取るために請求書で気を付けること
中小事業主が建設業許可を取るためには、「経営者としての経験」(経営業務の管理責任者)、「実務経験」(専任技術者)を証明するための資料として、該当期間の請負工事の注文書や請求書が必要となります。
しかし、請求書なら何でも認められるわけではなく、7つの注意点があります。
①通帳原本もしくは領収書の原本が必要
請求金額に対する入金を確認するため、通帳原本もしくは領収書の原本が必要です。②入金明細などが必要
請求金額と入金額に違いがある場合は、その違いを説明できる入金明細などが必要になります。③人工出し(人数×単価で金額が算出されたもの)の注文書、請求書は、経営経験の資料としては認められない
建設現場では、一人親方を貸し出す「人工出し」ということが度々行われています。この「人工出し」は、建設業の請負工事に該当しません。
そのため、建設業の経営経験として認められません。
例えば「屋根工事 一式」と記載されている注文書は中小事業主が屋根工事を請け負ったものとみなされますが、「人工単価2万円×3名」と記載されているものは、中小事業主が請負工事を請け負ったものとはみなされないため、注意が必要です。
④請求書の内容として、中小事業主が許可を受けようとする業種とわかる文言の記載が必要
例えば下記の様な業種名が必要です。大工工事・・・大工工事、型枠工事、造作工事
とび土工・・・解体工事、掘削工事など
電気工事・・・発電設備工事など
管工事 ・・・冷暖房設備工事など
防水工事・・・シーリング工事など
内装仕上・・・内装間仕切り工事、床仕上げ工事など
⑤どの業種の工事か確認できる別途資料(見積書、内訳書、工程表、図面など)が必要
請求書の内容として、増築、改修、リフォーム工事等となっている場合や、現場名しか書かれていない場合は、どの業種の工事か確認できる別途資料(見積書、内訳書、工程表、図面など)が必要になります。⑥5年以上の経営経験を証明できる
最も古い請求書の請求日から、最も新しい請求書の請求日までが5年以上であることが必要です。⑦各年に最低1件の注文書もしくは請求書が必要
経営経験の証明のために、各年ごとの注文書もしくは請求書の用意が必要となります。⑥⑦について例えば、中小事業主が5年以上の経営経験を証明するために、請求書を用意することとします。
まず、最も古い請求書の請求日から最も新しい請求書の請求日までで、5年以上必要となります。
最も古い請求書が平成25年10月11日、最も新しい請求書が平成30年10月10日では、5年以上となりません。1日だけ足りていません。
最も新しい請求書が平成30年10月12日あれば、5年を超えるため問題ありません。
1日でも足りてない場合は要件を満たさないことになるため、注意が必要です。
次に各年に1件の請求書が必要となります。
先ほどの例でいうと、平成25年と平成30年は上記で用意されたもので問題ありませんので、残りは平成26、27、28、29年の請求書を用意する必要があります。
これら4年分については、何月のものでも問題ありません。
ネット加入は事務組合RJCしかできない!
事務組合RJCしかできません!
「ネットで加入ができる」
「ネットで見積もりができる」
「会員カードの発行がとにかく早い」
特別加入(特別労災)が必要だけど、手続きをしに行く時間がないなら、事務組合RJCに申込み。
ゼネコンが選ぶNo.1から、間違いありません。
5.建設業の請求書:まとめ
建設業の中小事業主が作成する請求書においては、人工計算や出来高払いなど一般的な取引とは異なる仕組みがとられています。
中小事業主が請負元とのトラブルを未然に防ぐためにも、契約書を前提とした必須項目だけでなく、請負元が推奨するフォーマット等を使用して分かりやすい請求書を作成することが大切です。
推奨フォーマットがない場合でも、請求書を手間なく作成できるシステムやツールが多数販売されていますので、活用するのも一つの方法でしょう。
いざ建設業許可を申請する場合に困らないよう、中小事業主は普段からルールに沿った請求書の作成・保管をすることが大切です。

RJCグループ アドバイザー
林 満
はやし みつる
現在は、RJCグループアドバイザーや大手ゼネコン竹中工務店名古屋支店 労災業務を担当しながら、労災保険特別加入制度の普及や災害防止活動に取り組んでいる。